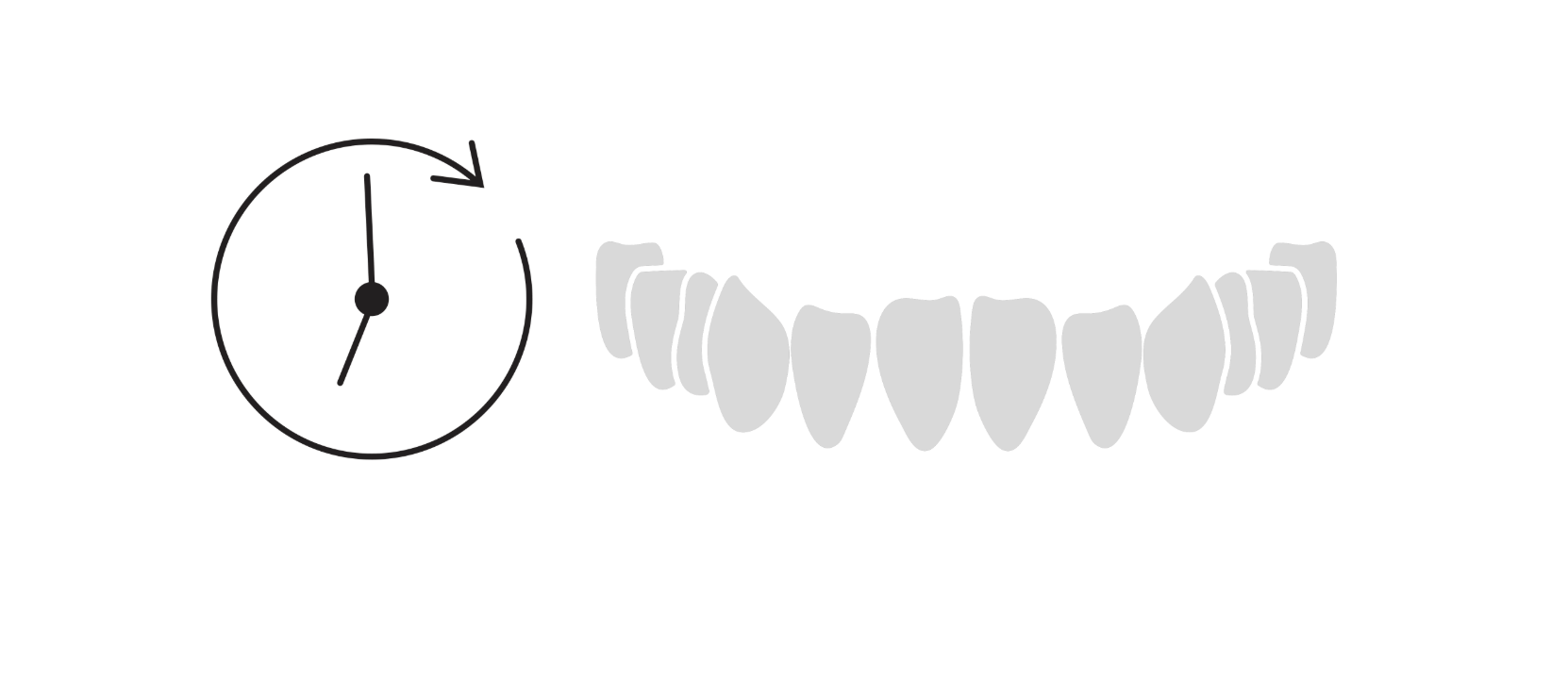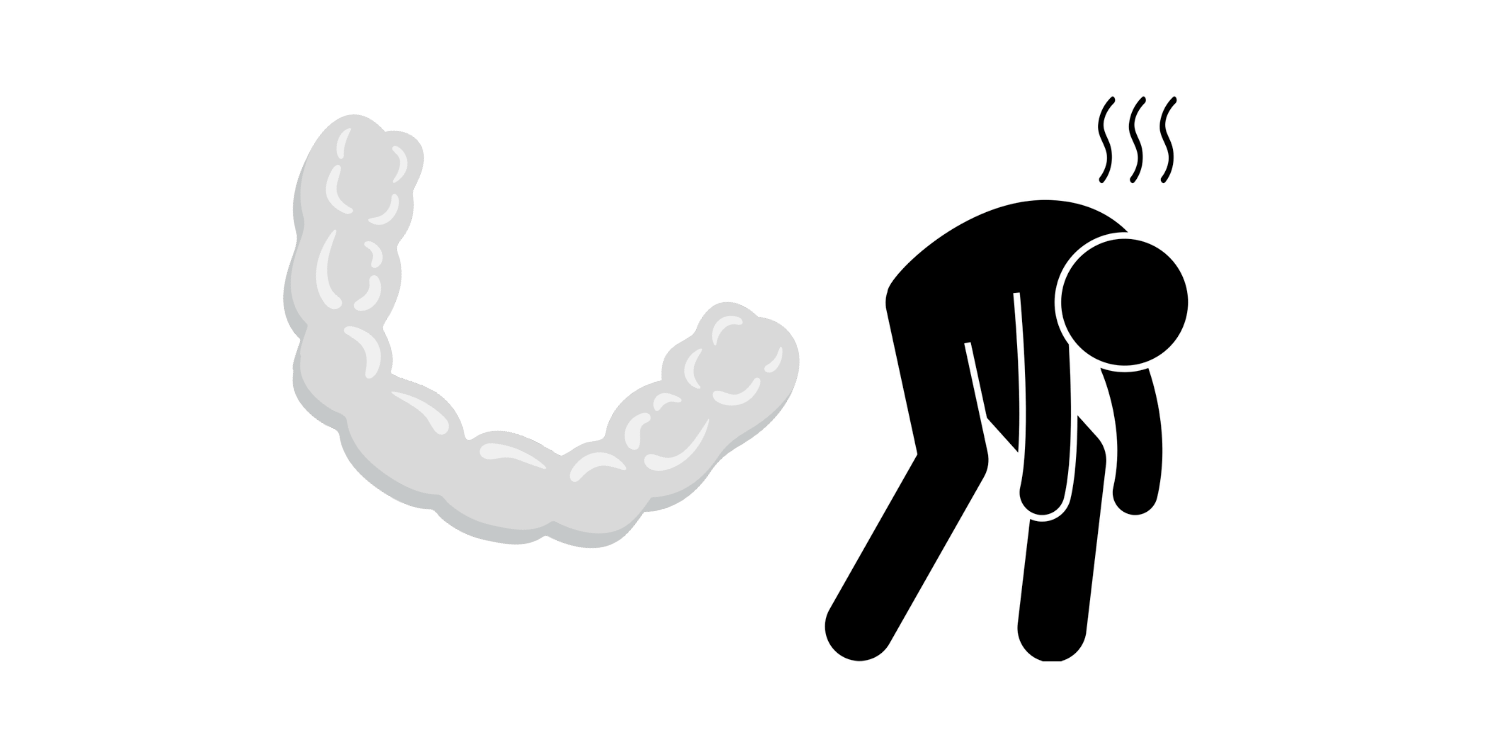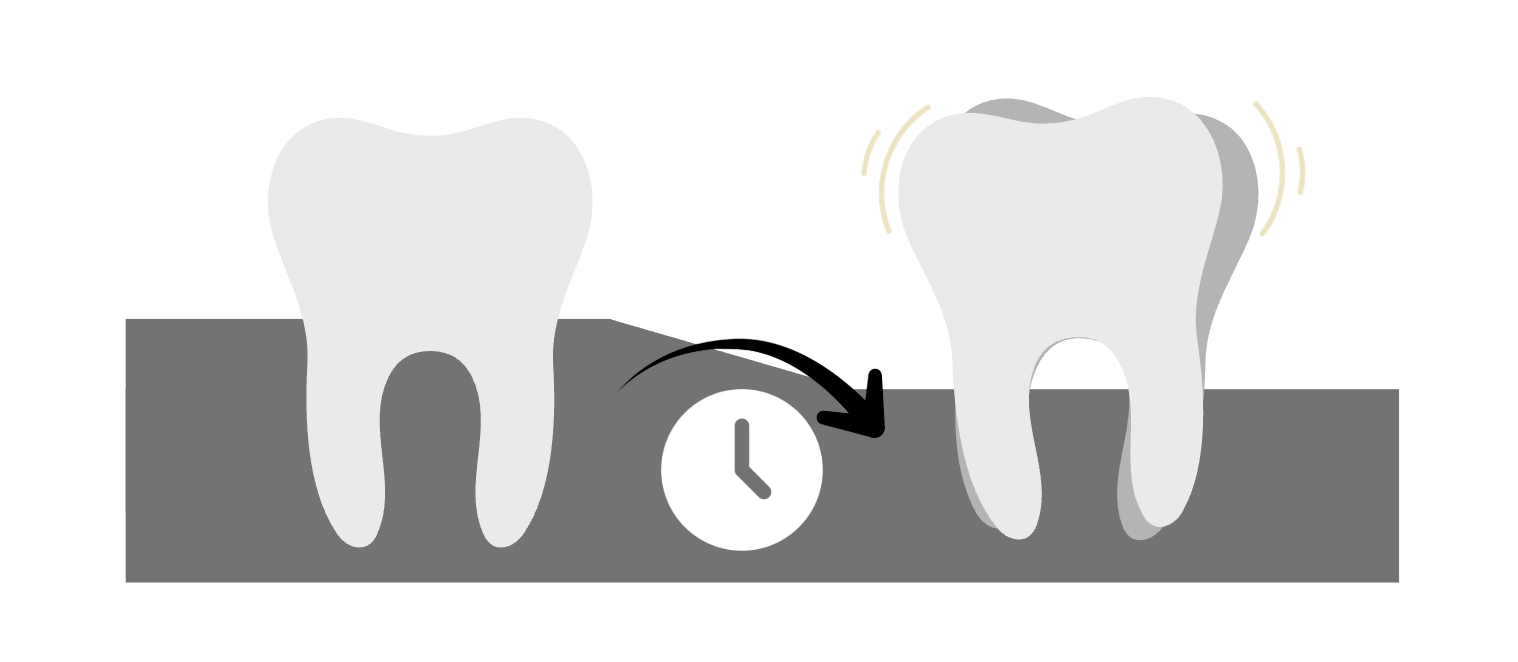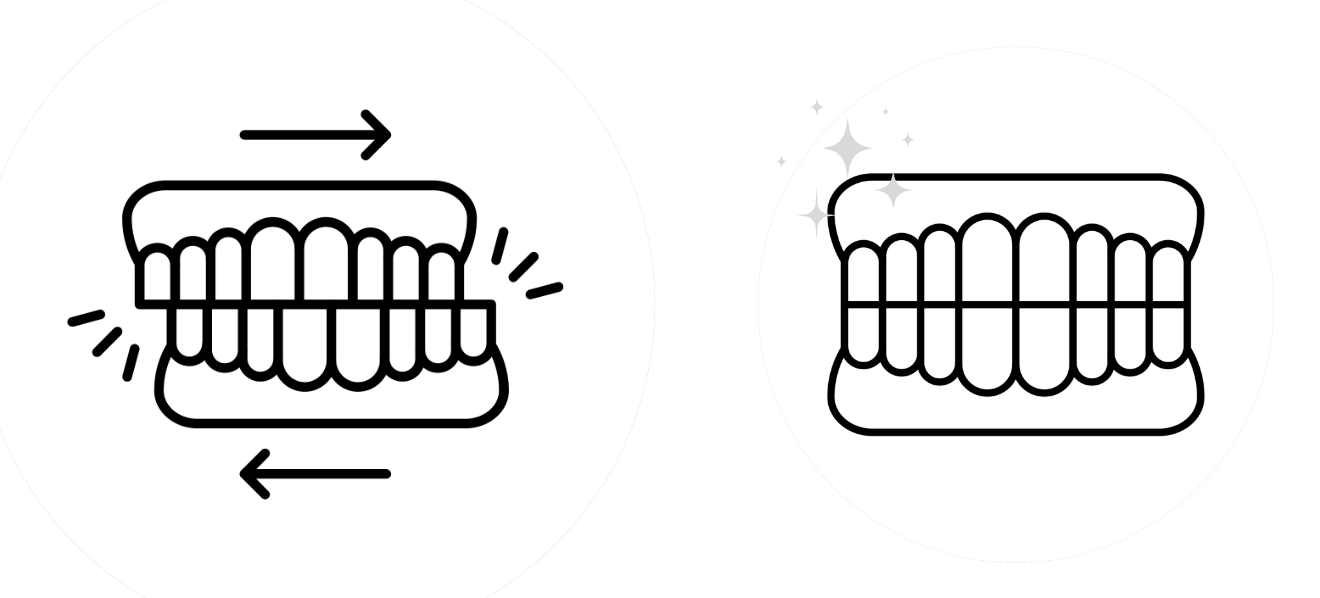矯正治療後の後戻り(患者さんに伝えるべき真実)
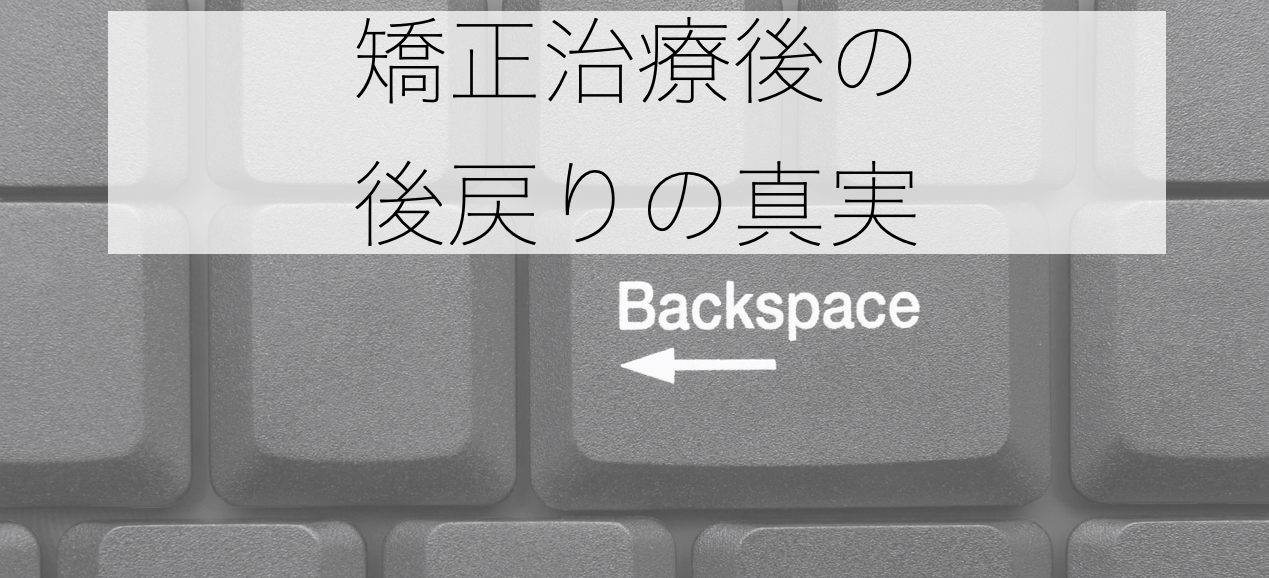
目次
矯正治療を終えた患者さんから「最近、少し歯が動いてきた気がする」という相談を受けることがあります。実は、矯正治療後の後戻りは決して珍しい現象ではありません。
むしろ、ある程度の後戻りは「避けられない自然現象」として捉えるべきです。今回は、矯正治療の後戻りについて、論文報告に基づいた本当の情報を説明します。
後戻りはなぜ起こるのか
矯正治療で歯を動かすと、歯を支える骨や歯茎、靱帯といった組織も一緒に変化します。しかし、これらの歯周組織は元の位置を「記憶」しており、矯正治療後の新しい位置で完全に安定するまでには相当な時間がかかります。最も驚くべき研究結果は、矯正力を除去してからわずか2時間以内に後戻りが始まるという報告です。これは1960年代のReitanによる研究で明らかにされました。
さらに興味深いのは、この「記憶」が治療後数年経っても残る可能性があることです。コラーゲン線維の代謝は比較的速いのですが、オキシタラン線維、プロテオグリカン、グリコサミノグリカンなどの他の細胞外成分が、長期的な後戻りに関与していると考えられています。
実際、矯正治療後10~20年経過した患者の40~90%に歯並びの乱れが見られるという研究報告があります。つまり、矯正治療直後だけでなく、何年も経ってから後戻りが起こることは避けられないです。
リテーナーを使用していない場合、後戻りの速度と程度はさらに顕著になります。矯正治療後最初の3か月では、患者さんの約69%が毎晩リテーナーを装着していますが、約2年後には指示通りに使用をしている患者さんは45%まで低下していると報告もあるくらいです。
さらに、19%の患者は全く装着しなくなってしまいます。その際、リテーナーは「力ずくで歯を抑えている」装置の面もあり、やめれば即座に後戻りプロセスが始まるケースもあります。
永遠の効果はない
矯正治療において最も重要なのは、治療開始前の適切なインフォームド・コンセントです。しかし、患者さんは治療について細かいところまで理解をすることは、本当に難しいことです。診断時のインフォームド・コンセントの説明直後に行われた調査では、患者さんは、矯正歯科医が説明した治療の理由、処置内容、副作用とリスクについて、いくつかの項目しか思い出すことができません。特に、後戻り、虫歯、歯茎への影響などに関する重要なリスクの記憶率は非常に低いと言えます
アメリカの矯正歯科医を対象とした調査では、回答者の9.1%が医療訴訟を経験しており、非臨床的な訴訟の原因として最も多かったのは、患者からの適切なインフォームド・コンセントの失敗で39%を占めています。多くの患者は「矯正治療の効果は永遠」と勘違いしており、後戻りが起きてから初めて現実を知ることになります。この認識のギャップが、患者さんの不満につながるのです。
アメリカ矯正学会の推奨する同意書では、「矯正治療の完了は、生涯にわたって完璧にまっすぐな歯を保証するものではありません」と明記されています。また「一部の歯並びは元の状態まで戻る傾向があります」という記載もされていることがあります。
治療開始前に、後戻りは基本的に避けられない現象であることを明確に伝えることが、医療過誤訴訟を防ぐだけでなく、患者さんとの信頼関係を築く上でも不可欠になっています。
習慣化できる人はごくわずかという現実
矯正治療後の長期的な成功は、リテーナーの継続的な使用にかかっています。しかし、人間の行動変容を長期的に維持することは想像以上に困難です。これはダイエットのリバウンドと本質的に同じ問題です。装置除去後のリテーナー装着の順守率は、1~2年で64.3%、2~3年で64.7%、、3~4年で60%とアメリカの文献では報告されており、時間とともに徐々に低下していきます。
したがって、固定式リテーナー(フィックス)を設置を希望される患者さんもいます。しかし、固定式リテーナーの5年追跡調査では、故障による保定の失敗率は54%という非常に高い値になっており、5年生存率は半分も満たない状態です。しかも、失敗の83%が治療後1年以内初期に発生しており、「固定式だから安心」というわけではないのです。
リテーナーを装着しない理由として最も多いのは「不快感」と「忘れてしまうこと」です。これは意志の問題ではなく、人間の行動パターンとして自然なことです。
実際、歯周病のメンテナンスに関する成人のコンプライアンス研究では、3か月フォローアップに戻ってきたのはわずか30%でした。医学全般においても、患者の25~50%がコンプライアンスに失敗することが示されています。
このような現実を踏まえると、リテーナー使用を長期的に継続できる自信がない患者には、そもそも矯正治療を勧めないという判断も、倫理的かつ臨床的に正しいアプローチと言えます。
矯正治療は何度もやり直せるものではありません。初診相談の段階で、長期的な歯並びの管理に対するコミットメント能力を評価することが重要になってきます。
エイジングによる歯の移動は避けられない変化
矯正治療後の歯の移動を考える上で見落とされがちなのが、エイジングによる自然な変化です。実は、矯正治療を受けていない人でも、年齢とともに歯は移動し続けています。
口腔周囲筋のバランスは年齢とともに変化し、歯列が狭くなったり、前歯が突出してきたりすることは自然な現象なのです。舌の位置や唇・頬の筋肉の緊張度が変わることで、歯に加わる力のバランスが変化し、徐々に歯が移動していきます。
さらに、歯の磨耗も避けられません。長年の咀嚼や歯ぎしりにより、歯の咬合面や切縁は少しずつすり減り、これが咬合関係や歯列の形態に影響を与えます。歯周組織もエイジングとともに変化します。歯茎が下がることで歯根が露出し、歯を支える骨の量も徐々に減少していきます。歯周組織が弱くなると、歯は以前よりも動きやすい状態になり、わずかな力でも位置が変わりやすくなるのです。
特に重要なのは、審美的な観点からの変化です。歯茎が下がると歯が長く見えるようになり、歯の変色も進行します。また、歯の先端が磨耗したり欠けたりすることで、歯の形態も変化していきます。
エイジングの変化は、笑ったときの前から見た歯並びのイメージを大きく変えてしまいます。矯正治療で完璧に並べた歯列も、歯茎の退縮や歯の変色により、印象が全く異なって見えることがあるのです。
見落とされがちなのが、歯科治療の影響です。むし歯治療で詰め物や被せ物を入れる、抜歯してブリッジやインプラントを入れる、義歯を装着するなど、様々な歯科治療が咬合や歯並びに影響を与えます。特に奥歯の治療は、前歯の位置にも波及的な影響を及ぼすことがあります。これらを考えると、矯正治療終了時点の状態を永遠に維持し続けることは、ほぼ不可能と言わざるを得ません。
重要なのは、エイジングによる変化を「後戻り」と混同しないことです。真の後戻りは矯正治療による歯の移動に対する反応ですが、エイジングは自然な老化現象です。矯正治療を受けていない人でも同じような変化は起こります。
したがって、患者さんには治療前から「ある程度のエイジングは受け入れる必要がある」ことを理解していただくことが大切です。完璧な歯並びを一生維持することではなく、機能的で健康的な口腔環境を長期的に保つことが、現実的な目標なのです。
咬合改善と審美改善で後戻りのリスクは異なる
矯正治療の目的は大きく「咬合の改善」と「審美的改善」に分けられますが、実はこの2つでは後戻りのリスクが大きく異なります。
機能的な咬合改善、例えば過蓋咬合や反対咬合の改善などは、適切な咬合接触により機械的に安定しやすい特徴があります。ラットを用いた研究では、咬頭と窩の間の嵌合接触を持つグループは、後戻り移動、炎症因子、破骨細胞活性のレベルが最も低かったという結果が出ています。
一方、審美的な改善、特に叢生の解消や前歯の配列改善、空隙の閉鎖などは、機能的な安定機構が少なく、歯周組織の「記憶」や軟組織の圧力の影響を受けやすいのです。安定した咬合は、上下顎の歯列間の適切な咬合関係と関連しており、咬合干渉や歯の接触のずれ、咬合過負荷は後戻りのリスクを増加させます。
矯正治療では、歯を「中立帯」と呼ばれる、舌の遠心力と口唇周囲軟組織の求心力が均衡する領域に配置することが理想ですが、審美目的の治療ではこの原則を満たすことが難しい場合があります。
患者さんが後戻りを実感しやすいのも、主に審美的変化です。前歯の叢生の再発、空隙の再開、前歯の前突の再発など、これらは鏡で見える変化であり、日常的に気づきやすいのです。
しかし、機能的な咬合の微妙な変化は患者自身が気づきにくいことがあります。実際、小臼歯抜歯治療を受けた症例のうち、良好な下顎前歯配列を維持したのは約30%のみで、2/3が後戻りしたという報告もあります。
保定のない歯列では、矯正仕上げの質が良好であっても前歯部配列の安定性は保証されないという研究結果もあり、審美目的での歯の移動が必ずしも機能的な安定位置と一致しないことを示しています。したがって、審美を主目的とする患者には、より厳格なリテーナープロトコルと長期的なフォローアップが必要となります。
矯正治療後10年で満足のいく歯並びを維持できるのは30〜50%のみ、20年後では10%しか臨床的に満足できる状態を維持できていないという長期研究のデータは、この現実を如実に物語っています。
まとめ
矯正治療後の後戻りは避けられない自然現象です。歯周組織は元の位置を「記憶」しており、矯正力を除去すると即座に歯は動き始めます。リテーナーの長期的な使用は困難で、多くの患者がコンプライアンスを維持できません。
さらに加齢による口腔周囲筋のバランス変化、歯の磨耗、歯周組織の変化により、歯は自然に移動し続けます。治療前に後戻りとエイジングの現実を患者に正直に伝え、適切な期待値を設定することが重要です。そして、矯正歯科医は長期的なリテーナー使用を守れる患者さんに慎重に治療を勧める必要があります。
よくある質問
Q1: リテーナーは一生使い続けなければいけないのですか?何年くらい使えば安定しますか?
後戻りのリスクを最小限にしたい場合はリテーナーは一生使用した方が望ましいです。また、使用年数と安定性に相関性はありません。
Q2: 固定式リテーナーが、壊れた場合はすぐに後戻りしてしまいますか?
すぐには戻りませんが、ワイヤーが歯から外れていることに気づかず、数か月が経ってしまうと後戻りしてしまいます。なかでも、隙間やねじれは1か月経たずに後戻りが始まります。
Q3: 「リテーナー使用を長期的に継続できる自信がない患者には矯正治療を勧めない」とありますが、それでも治療を希望する場合はどうなりますか?
リテーナーを使用しなくても全部後戻りするわけではありません。ある程度の後戻りは許容することをご理解の上、矯正治療を行うと良いでしょう。
【記事執筆者の略歴】
牧野 正志
徳島大学歯学部卒業 (2006)
東京歯科大学 歯科矯正学講座 研修課程修了 (2010)
まきの歯列矯正クリニック開設 (2012)
日本矯正歯科学会 認定医・臨床医